
- 設計:
- 荒川 圭史
- インテリア:
- 赤堀 ゆか
- 竣工:
- 2016年03月
- カテゴリ:

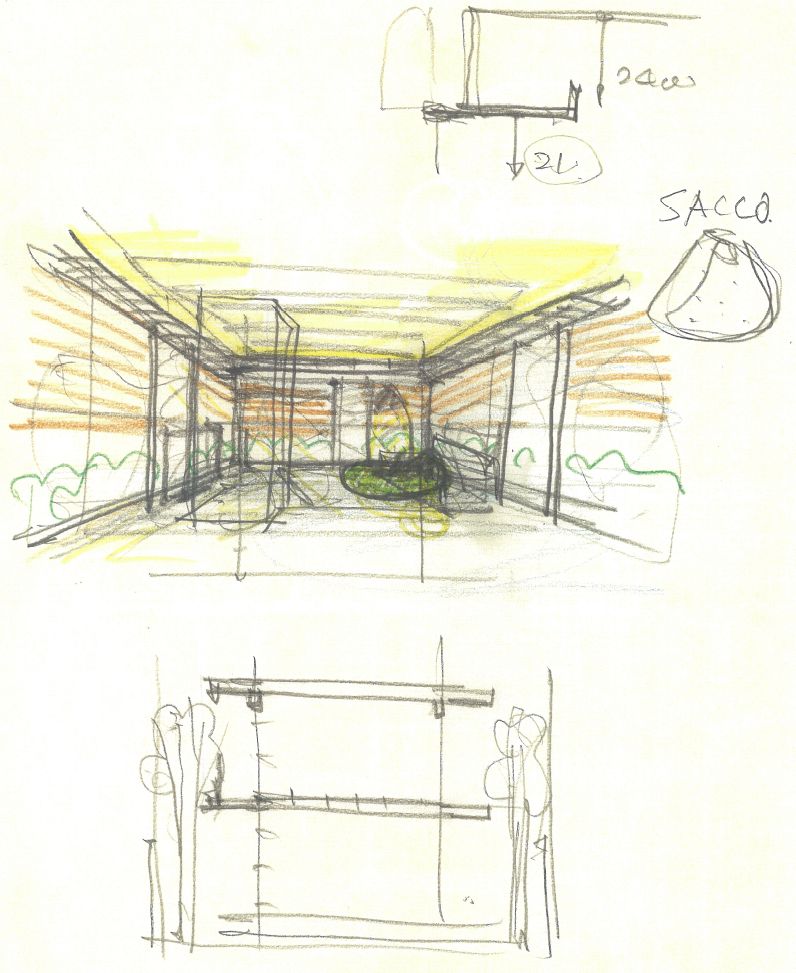

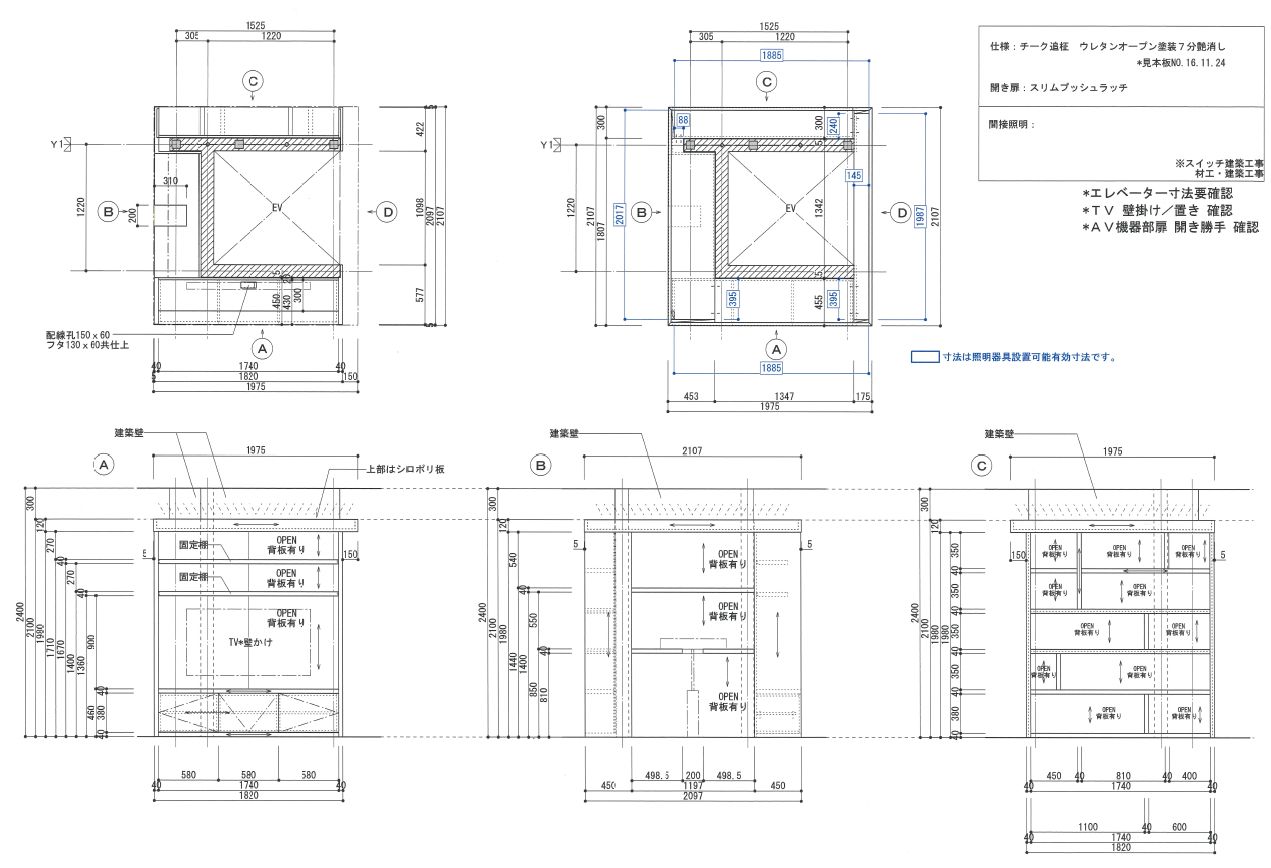



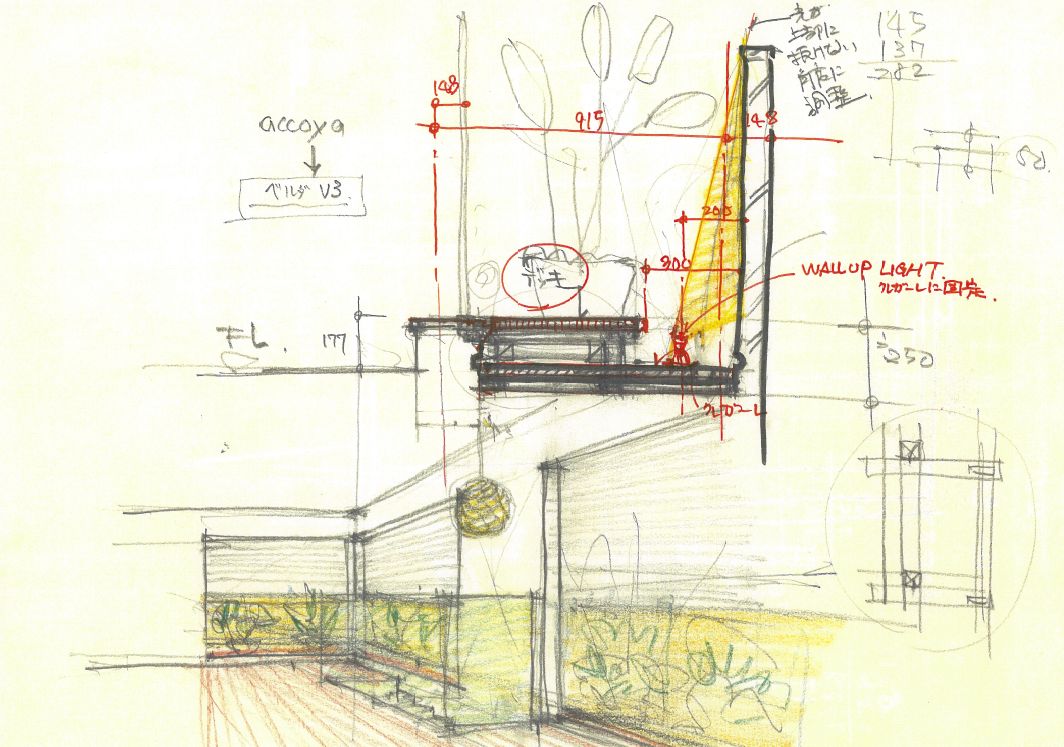



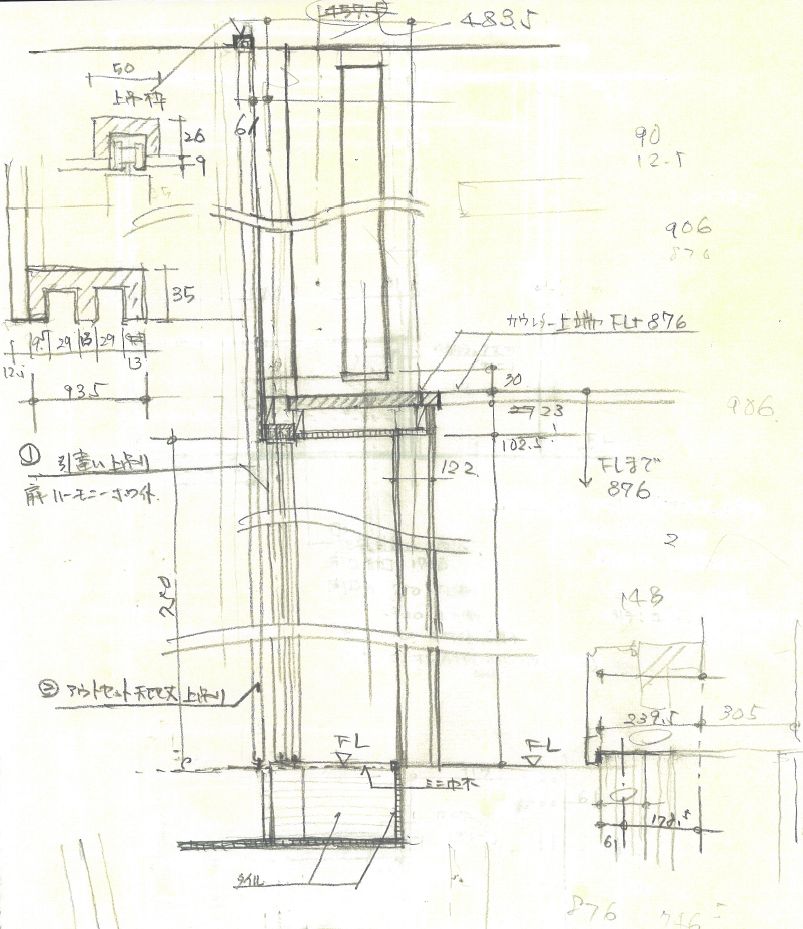




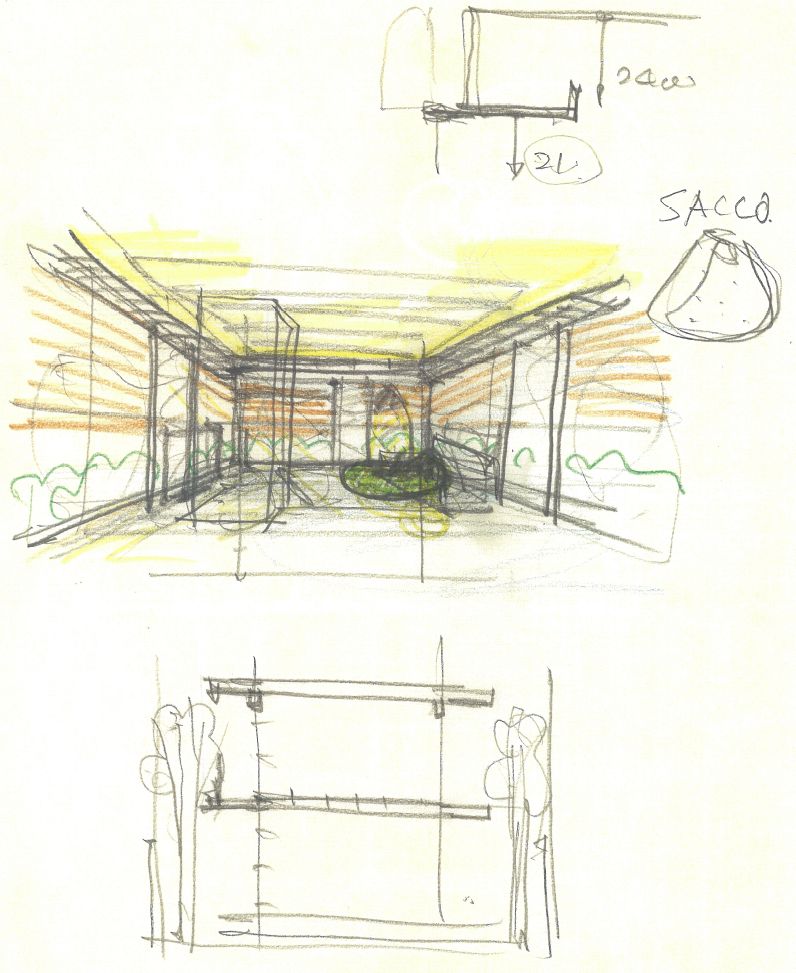

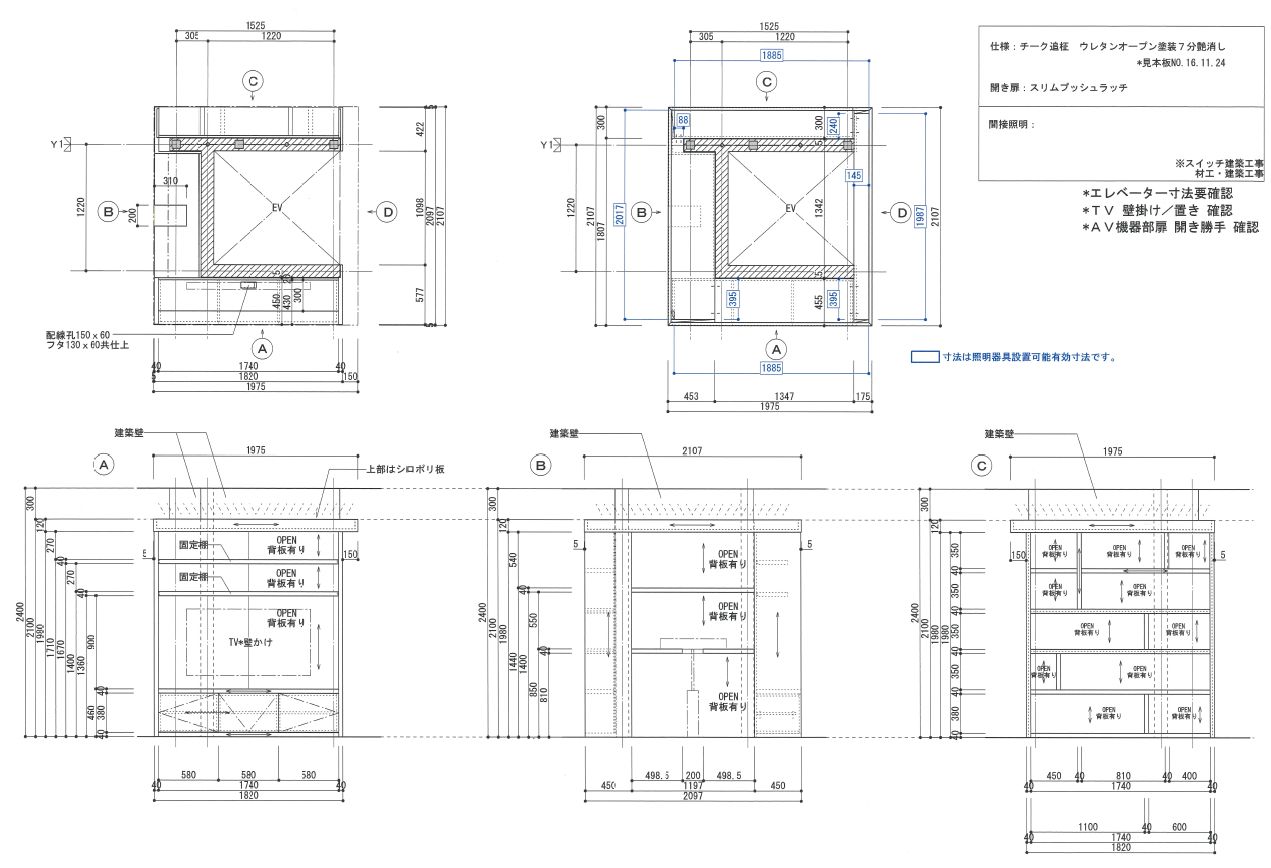



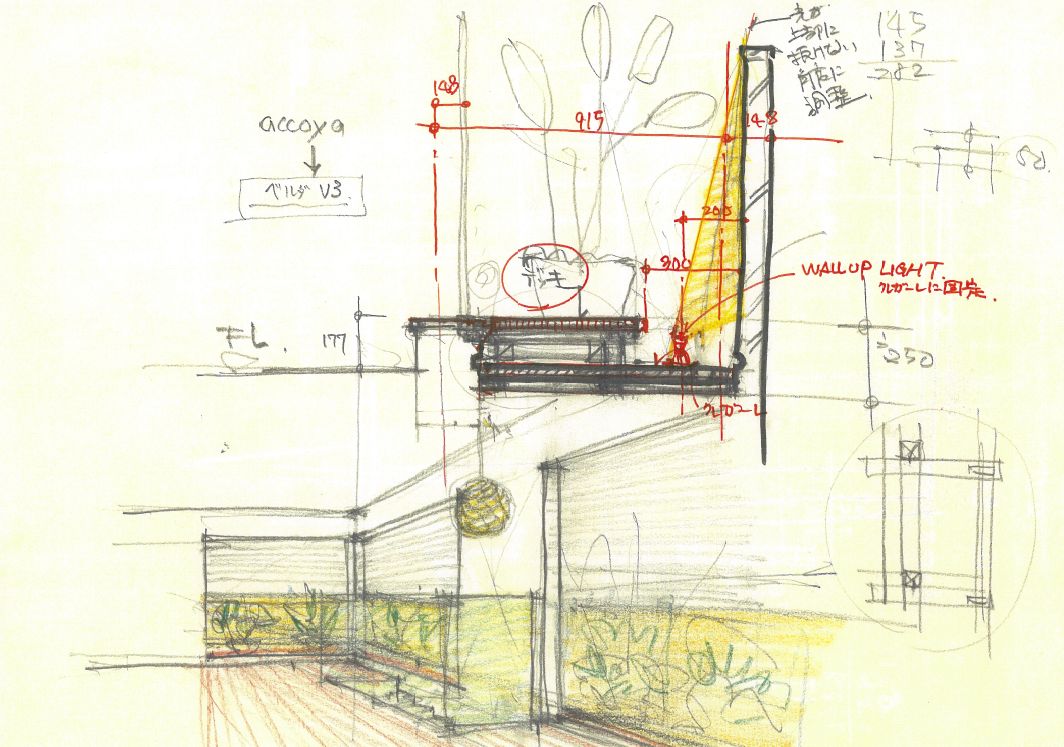



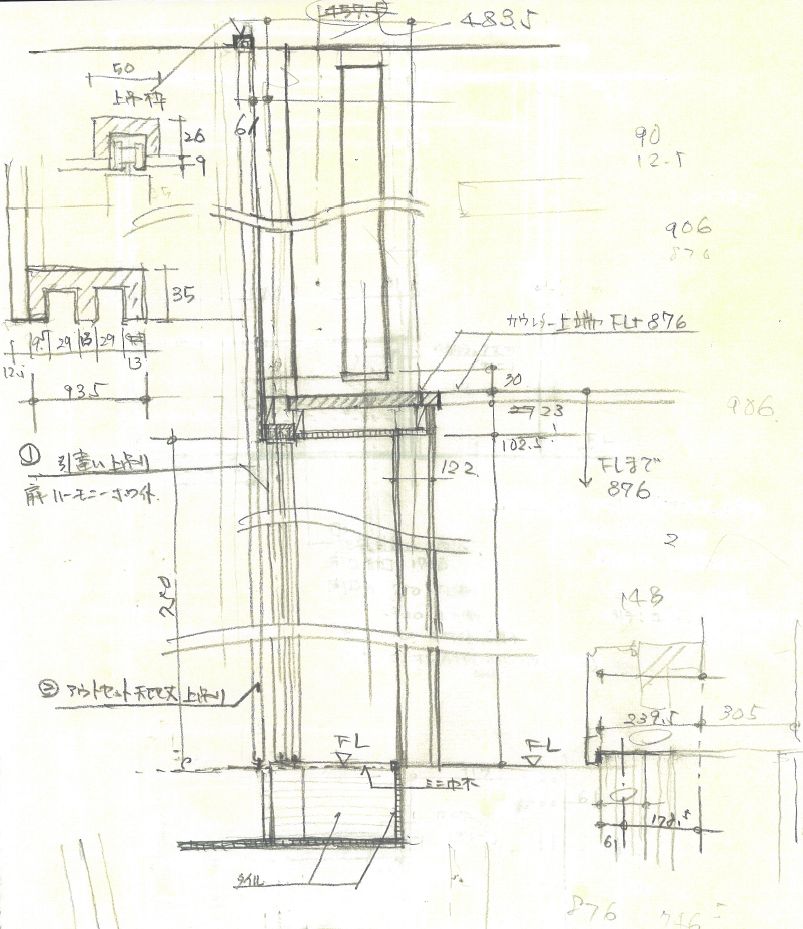

東京デザインオフィスでは
家づくりのご相談をいつでも承っています。
最新の建築実例集もご用意しておりますので、
お気軽に下記連絡先からお問い合わせください。
0120-040-744
受付時間/9:00~18:00 定休日/火曜日・水曜日
部屋を借りたい
お住まいの方・オーナーの方
オーナー様向けサービス